【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.53『夏至と焼きサバ寿司』
つくばで食べる・つくる・育てる
6月のテーマ「夏至と焼きサバ寿司」
こんにちは、くーこです。
しゅわしゅわの飲物がおいしい季節になってきましたね。最近は炭酸水にレモンとミントを入れるのがお気に入りです。窓を開けながら息子とレモンソーダを飲んでいたら、うぐいすの鳴く声が聞こえました。お隣さんのお庭には梅や椿などがたくさん植わっているので、それ自体は珍しいことではないのですが「この時期にうぐいすっているっけ?それにしてもすごく良い声して鳴くねえ」と息子もびっくりしていました。なので、通年うぐいすは存在しているが春に番を探してよく鳴いているから認識しやすいこと、鳴けば鳴くほど上手になっていくことを説明したらしょっぱい顔になって「つまり、婚活失敗してるってこと?」と尋ねてきたのでYes!と答えました。「早くパートナー見つかるとよいね」とうぐいすの幸せを祈らずにはいられない昼下がりでした。
![]()
閑話休題、私は夕飯後にウォーキングをしているのですが最近暗くなるのが遅いなあと感じていたら、カレンダーの6月21日に「夏至」と書いてあって納得です。夏至とはご存じの通り、1年で一番昼の時間が長い日のことです。私の中で夏至と言えばムーミンで、『ムーミン谷の夏まつり』や『ムーミン谷の仲間たち』に夏至の話が出てきます。夏至の前夜にニョロニョロが生まれるとか、物語の中だけの話だと思っていた枕の下に9種類(現在は7種類で良いらしい)の花を置いて寝ると夢で将来の旦那様に会えるとか、お祭りで焚いていたかがり火もフィンランドでは「コッコ」と呼ばれ悪縁を断ち切って良縁を結ぶ昔からの風習なんだそうです。
その他、ヨーロッパ各地で夏至のお祝いをするそうで、スウェーデンではミッドサマーと呼ばれるお祭りがあり、ニシンの酢漬けや新じゃがをおつまみにしてビールやスウェーデンウォッカを楽しむのだそう。有名なところだと、イギリスのストーンヘンジですよね。諸説ありますが、紀元前2500年頃の神殿で、夏至の日には祭壇から少し離れたところにあるスローターストーンと隣に立っているヒールストーンの二つの石の間を抜けて祭壇石に陽が射すそうです。非常に神々しい感じがしますね。
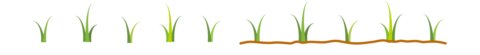
と、ヨーロッパでは夏至がかなり重要なものらしいのですが、日本ではあまりお祭りとか聞かないですね。神社で行われる夏越の祓ぐらいかも。その理由のひとつに夏至から半夏生の間に田植えをしていたから。昔は今よりずっと遅かったのですね。そんな忙しい時期にお祭りなんてしていられませんが、その代わりに豊作を願う食べ物を食べたり、お供えする風習は各地にあるそうです。最近は関東にも根付きつつありますが、半夏生にタコを食べるのは大阪周辺の風習で、稲がタコの吸盤のようによく根付くようになんだとか。他にも冬瓜・和菓子の水無月・三重県のみょうが・福井県の焼きサバがあるそうです。関東では新小麦の焼き餅があるそうなのですが、生まれて一度も食べたことがないです。

せっかくなので、縁起物の焼きサバとミョウガを使って焼きサバ寿司を作ります。作り方は非常に簡単。スーパーで塩サバ(骨抜き済み。ノルウェー産が脂のってておススメ)を買って、焼いて、酢飯と合わせて、ラップでぐるぐる巻いて出来上がりです。身の厚いところの皮面に包丁で切れ目を入れて焼くと皮がパリパリになっておいしくなりますがやってもやらなくてもOK。酢飯に薬味をたくさん入れるのでさっぱりとしていて夏向きな味です。包むのがめんどくさい人は焼きサバをほぐして薬味入り酢飯にかけると、そぼろ丼みたいでこれはこれでおいしいです。〆鯖が苦手な人でもこれなら食べられると思いますよ。ちょっぴり夏バテ気味な時にピッタリな気がします。
今年も猛暑になりそうなので、モリモリ食べてのりきりたいですね。
それではまた、7月にお目にかかりましょう。
![]()
≪焼きサバ寿司≫
・炊き立てのご飯 1合分
・すし酢 大さじ4
・大葉 6枚
☆塩こんぶ 大さじ1
☆白ごま 大さじ1
☆寿司ガリ 20g
☆みょうが 2本
塩こんぶと寿司ガリは刻んででおく
① 塩サバは皮面に細かく斜めに切れ目を入れて、グリルかフライパンで両面こんがり焼いてそのまま置いておく
② ボウルに炊き立てのご飯とすし酢を入れて切るように混ぜたら、☆を入れて軽く混ぜる
③ 大きめに切ったラップの下側に皮目を下向きにしたサバを置いたら、その上に大葉3枚を敷き、②の半量を軽くまとめながら大葉の上に置いていく
④ 手前のラップを持ち上げ、巻いていく。ラップの向こう側を引っ張りながらきつく巻き、両端は最後に折り返し全体を棒状に整える
⑤ 30分くらい冷蔵庫で休ませたらできあがり。切る時はラップごと切るとうまくできます
![]()
執筆者紹介: くーこ さん
つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。
学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。
趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。
コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。