Posts in Category: お知らせ
【コラム】苔玉に寄せて Vol.120~苔玉その後
年末年始に渡って多種の植物を苔玉に仕立てました。シクラメン、カランコエ、ミニチュアローズ、小型のコチョウラン等の比較的洋風な花物等々、また、クロマツ、アカマツ、ゴヨウマツ、ウメ、ミリオンバンブー、マンリョウ、ヒャクリョウ、ジュウリョウ等の和風植物・・・・・でした。
苔玉に仕立てたこれらの植物を観て・・・・・「この苔玉、何年持ちますか?」と質問されることしばしばです。とくにマツ、ウメ等の『木本植物』の苔玉については、3~5年と永年に渡って苔玉仕立てのままで持たせ続けたい・・・・・そんな期待感をお持ちの心を垣間見ます。マツという永年植物を苔玉仕立てのままで維持し続けたい・・・・・その心の内は解ります。でも苔玉なる『狭隘な台地』で植物を維持管理し続けることは、殆んど無理・難題です。
高分子化学の発達の一面として、プラスチック製の植木鉢やプランターが大量に出回る今日、自然志向を好む園芸に親しみ・愛する人たちは、工場出荷製品プラ鉢を忌避する傾向があります。せめてプラスチック製の植付容器を自然のモノに変えてみたい、その思いの一つの現れが、鑑賞植物を」『苔玉』に仕立てる・・・・・ということになったのではないでしょうか。新春を寿いだマツ、ウメ、マンネンチク等の苔玉を、そのままの苔玉姿でいつまでも維持したい、その心は理解できますが、当のウメ、マツたちにとっては、誠に狭隘・厳しい生育環境です。
出来るだけ早急に鉢植に戻す、そして来年の新春に苔玉に衣変えして楽しむ・・・・・それが、植物たちが喜ぶ生育体系のようです。私たち園芸を嗜む者の年中行事の一環として、お考え頂いては如何でしょう。年末の生活空間に彩りを添えてくれたシクラメン等の草本植物については、苔玉から鉢植への栽培返還は感覚的に受入れやすいと思います。マツ、ウメそしてシクラメンを、私たちのライフサイクル・季節感格・年中行事にあわせて『切花』感覚で楽しむ・・・・・程の感覚で馳せています。
次は、節分にヒイラギを苔玉にしてメザシを下げて楽しむ、2月14日バレンタインの日には真紅のミニチュアローズの苔玉を、更に3月3日を目指してハナモモの苔玉を準備するなど、年中を風流心を持ちたい、老いの一徹・日々を過ごしております。

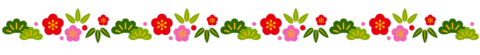
執筆者紹介 – S.Miyauchiさん
日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。
コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。
新年あけましておめでとうございます
皆さま、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
いつもActiveNoteをご愛顧くださり、誠にありがとうございます。
皆さまに支えられて ActiveNote は無事に11年目のスタートを切ることができました。
店頭で「すてきですね」「かわいいですね」と緑の苔玉を眺めてくださる皆さまの様子を拝見できることは、私たちにとって大切な宝物です。
苔玉教室で皆さまの楽しそうな笑顔に出会えること、そして「どうやって育てたらいいの?」といった素朴な疑問を共有していただけること。その一つひとつが、私たちが苔玉の魅力を伝え続ける原動力になっています。
園芸や盆栽の世界は、入り口が少し難しく思えるかもしれません。だからこそ、まずは「緑の苔玉」という形から、暮らしの中で気軽に緑を愛でる楽しさ、緑に癒される生活を感じていただければ嬉しいです。
11年目も、皆さまの暮らしが瑞々しい緑で彩られるよう、心を込めて尽力していく所存です。
本年もActiveNoteをどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和8年 元旦
ActiveNote スタッフ一同
【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.72 『冬野菜がおいしい季節になりました』
つくばで食べる・つくる・育てる
12月のテーマ
「冬野菜がおいしい季節になりました」
こんにちは、くーこです。冬野菜がおいしい季節になりましたね。
大根、白菜、水菜に青梗菜と去年の冬野菜は高温と天候不良で非常に価格が上がっていたのですが、今年は豊作とのことでつくばでは求めやすいお値段で並んでいます。ありがたいことに、知人の農家さんからは毎週たくさんの野菜をおすそ分けしていただき、野菜バイキング状態で小躍りしている毎日です。
特に我が家で人気なのが、大根と春菊です。
この時期に取れる大根は寒さの中でじっくりと育てているため、甘みと旨味が凝縮されていて、煮ればとろけるような食感になり、サラダや大根おろしの様にそのままで食べても甘くてとてもおいしいです。年末年始はお餅をよく食べるのですが、たっぷりの大根おろしの中に納豆を入れて醤油かポン酢で味付けした中に、茹でたお餅を入れて絡めた「納豆からみ餅」が人気です。気を付けないとお餅が3個ぐらいするするっと胃袋に吸い込まれてしまう危険なヤツです。あっさりしているので気持ちは0カロリーなんですけれど、餅ですからね、要注意なのです。

大根と言えば、スーパーに売られているものには見かけることが少ないですが、葉っぱもおいしく食べられます。しかも栄養満点。ビタミンA・C、カルシウム、鉄分、食物繊維などが豊富に含まれています。特に冬の寒さの中で育った葉は、色鮮やかでシャキシャキとした食感が特徴です。普段は捨ててしまいがちな部分ですが、実は健康にも美容にも嬉しい栄養がぎゅっと詰まっています。ただ、足が早いので手に入れたら即調理するのをおすすめします。油と相性が良いので刻んでさっと炒めてお味噌汁の具にしたり、塩とゴマで味付けして菜飯の素をよく作っています。じゃこを入れると更においしいです。炊き立てご飯に混ぜて、おにぎりにすると最高に幸せになります。
春菊は昔はえぐみとか好きじゃない野菜ベスト3に入っていたのですが、採れたてだからなのか品種改良されたからなのか、独特の香りとほろ苦さがおいしいと感じられるようになりました。息子も茎のシャキシャキ食感が好きらしく、マヨネーズ和えや肉豆腐に入っていると喜んで食べています。
![]()
そして先日、中学生の息子が「学校でジャガイモを収穫したから」と2個持って帰ってきました。私のはるか昔の記憶では、小学4年生の時に春から初夏にかけて理科の授業でジャガイモを育てましたが、中学校?しかも今時期?話を聞くと、なんと最近では技術家庭の技術の時間に野菜を育てる課題があるそうです。土壌のリンや窒素などの割合とかも勉強するとのことなので、本格的な感じですね。そして、収穫した野菜を使って家庭科で調理をするのだとか。ジャガイモは秋に種芋を植えてお世話したそうです。調べてみると、ジャガイモって春と秋に植えて年に2回収穫できるのですね。今は夏が暑すぎるから秋植えの方がうまく育ちそうです。

お芋は息子からのリクエストで揚げ芋にして家族でおいしくいただきました。おいしさを引き出すため、冷たい油からジワジワ加熱して最後に180℃でカリッと仕上げます。食べてみると、初夏に取れるものより何となく甘みが強い気がします。冬の大根と同じ現象?ちなみに、この時お芋にはマコーミックから出ている「IRODORI(いろどり)」(少し前までは「サラダエレガンス」という名前で売られていました)という調味料をふりかけたのですが、今のミドルエイジが昔大好きだった人も多いはず、あのピザ食べ放題「シェーキーズ」のポテトとそっくりな味になります。カルディコーヒーファームなどで売られているので、興味のある方は購入してみてください。

授業では他にも大根も育てていて、そちらは他学年の調理実習に使われるそうです。「間引きした時に摘み菜サラダ感覚で食べたら皆にドン引きされた。カイワレ大根と一緒なのにね。あと、この間葉っぱだけ欲しいって言ったら(もちろん菜飯の素をつくるため)野生児って言われた。解せぬ、おいしいのに」とお芋をモグモグ食べながら教えてくれました。うん、お母さんもこれ以上ムーミンママって言われたくないから学校では少しお口チャックしてほしいなと思いつつ、家庭菜園の人参の葉っぱでかき揚げを作ろうとする私なのでした。
それではまた来年1月にお目にかかりましょう。
![]()
執筆者紹介: くーこ さん
つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。
学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。
趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。
コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。
【コラム】苔玉に寄せて Vol.119~寒中の苔玉
年末です、今期一番の寒い中で、マンリョウの苔玉作りにチャレンジしました。縁起を担いで赤実のマンリョウを一株、白実のマンリョウを一株、紅白取り揃えました。単純な一本立ちの樹形に飽き足らず、幹にアルミ線(径:2.5㎜)を巻きつけて樹形に変化をつけてみました。見事な紅白の『マンリョウの苔玉』になりました。緑色の葉っぱに包まれた小さな粒の赤と白の果実たちが、早々に新春をもたらしているかの如くです。

寒さ厳しい中で、みずみずしい緑・赤・白色を精一杯演じてくれる植物たちの息遣いに『感謝』です。万両と共に千両、百両(カラタチバナ)、十両(ヤブコウジ)、一両(アリドウシ、蟻徹し)を取りそろえると『金運』に恵まれる・・・・・
『万両・千両・百両・十両、有り通し!』だ、とか・・・・・
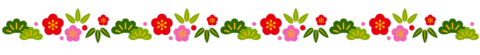
極めて狭くて小さな苔玉大地に、寒中にもかかわらず元気な生命力を見せてくれる植物たちです。油断すると枯らしてしまいます。新春を寿ぐ苔玉植物の代表に『マツ』を使うことが多いですが、『松の苔玉』を枯らしてしまったと耳にすること、しばしばです。原因は単なる水切れでした・・・!

マツ等の常緑樹は、冬でも葉っぱは元気な緑色です、少々水が切れた状態でも緑の姿を何とか維持しています。室内の空気はエアコンで乾燥・・・!緑色であったはずの松の葉っぱが茶色がかってきて、やっと水切れに気付く・・・という顛末。マツが枯れた、ツバキが枯れた、マンリョウ、センリョウもまた然り。冬季の空気は乾燥しています、更に煖房・エアコン等による強制乾燥・・・、植物たちも苔の台地も水切れ、気付いた時すでに手遅れ、という次第です。
一見しては、マツもツバキもマンリョウも緑色の元気そうな葉っぱです。気温が低いために急激な水切れ症状を表すことがない、ついつい苔玉の芯部分に水分が枯渇していることに気付かない、為に枯らしてしまう、という顛末。 噴霧器で苔玉表面に霧吹き潅水した積り、では間に合いません。苔玉の冬管理の基本は、やっぱり『水遣り』を忘れないことです。
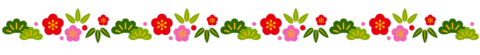
執筆者紹介 – S.Miyauchiさん
日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。
コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。
【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.71『りんごと過ごす秋のひと時』
つくばで食べる・つくる・育てる
11月のテーマ「りんごと過ごす秋のひと時」
こんにちは、くーこです。公園のイチョウが落葉し始め、ダッシュで秋が通り過ぎていきましたが皆様風邪など引いていませんか?最近、感染症予防には紅茶が良いと聞いたのでタンブラーにたっぷり入れて飲んでいます。
先月、実家の両親から長野旅行のお土産と、りんごを大量にもらいました。その量おそらく40個ぐらい。長野県の北部に位置する飯綱市で買ってきたリンゴでした。
長野県と言えばフルーツ王国で、四季折々においしい果物が取れますが、この飯綱市でひときわ輝くのが「りんご」。飯綱産のりんごについて、私の父が「今まで食べたリンゴの中で一番おいしい!あの世に行くまでにもう一度食べたい」と言っていたので、あの世に行く予定は全くないのですが今年の春に戸隠神社から山道を走って行ってみました。その時には白い花が咲き誇っていて、青空にとても映えていました。直売所では4月でも冷蔵貯蔵されたサンふじが販売されていて、パリッとしていてとてもジューシーなりんごで、確かにものすごくおいしかったです。その秘密は澄んだ空気と冷涼な気候、そして農家の皆さんの愛情らしいですよ。
![]()
両親は採れたてのサンふじを食べたくて飯綱に行ったのですが、残念ながら12月の上旬にならないと収穫時期にならないそうで、私に紅玉と初めて目にする青りんご…「ブレンハイムオレンジ」をどさっともたせてくれたのですが、調べてみるとクッキングアップルとのこと。イギリス原産で酸味が強く、荷崩れしやすいみたいです。ナッツのような独特な香りがあると書いてあり、どうやら飯綱市でしか作ってない日本では珍しい品種のようです。

つまり、これで何か作ってねってことのようです。とりあえず、すぐにできるアップルパイを焼きました。折角なので、種類別に焼いて食べ比べしてみます。冷凍庫にはパイシートが常備されているので、軽くソテーしたりんごを入れて、ツルヤで購入したあんずジャムをたっぷり塗って照りってりにしたら完成です。

酸味が強いリンゴでも甘みはそれなりにあるので、煮るときには正味量の1割のお砂糖を加えています。試食してみると、全く違う味わいで、紅玉のパイは「ザ・王道」というお味で甘みと酸味のバランスがとても良く、煮崩れしにくい品種なので歯触りも楽しめました。ブレンハイムオレンジは、酸味の中にコクがあってちょっと今まで食べたことがないお味でした。どうしても加熱すると煮崩れてしまい、ジャムっぽくはなってしまうのですが、それはそれでとてもおいしいのです。これだけ個性が強いのも珍しいかもしれませんね。2種類同時に食べるとどちらの良さも分かるのでその違いにびっくりしました。贅沢すぎる…



これに気を良くした私は、せっせとパイだけではなく、パンやケーキを作りまくりました。そんなある日、包丁が握れなくなるほど右手首に激痛が走り病院へ。先月のコラムにも登場したお医者様です。私の手首を見た瞬間「で、何剥いたの?栗はもう終わったんでしょ?柿か?」と言ってきたので「りんごです…お土産にたくさん調理用のりんごもらって…」と話すと、「あのくるくる回して皮剥くのは手首に負担かかるのよ。ここの筋がうんたらかんたら」と。「しばらくすれば治るから、それまでは作るの我慢しようね~。ところで、もらったりんごって紅玉?やっぱりアップルパイには紅玉が一番だよね!りんごと言えば…」と診察は1分で終わり、レントゲンどころか薬すら処方されず、先生の熱いリンゴトーク10分聞いて帰ってきました。その後常備薬のタイガーバームを塗ったおかげなのか先生の言った通り数日後には痛みもなくなりましたが、皆さんも皮を剥くときには割ってから剥くのが良いそうですよ。

さて、久しぶりのレシピはリンゴのパウンドケーキです。息子がお友達に作って持っていけるケーキを教えてほしいと言うので作ってみました。中に入れる煮りんごはお好みで加減してくださいね。今回は生地とほぼ同量入れましたが、ジューシーなケーキになりますよ。
それではまた12月にお目にかかりましょう。
![]()
≪りんごのパウンドケーキ≫
☆グラニュー糖 30g
☆ブランデー 大さじ2
☆シナモン 適量
*小麦粉 120g
*アーモンドプードル 30g
*ベーキングパウダー 小さじ1
・バター 100g
・卵 2個
・グラニュー糖 80g
・バニラエッセンス 少々
② バターをクリーム状になるまでよく混ぜ、グラニュー糖を加えて白っぽくふんわりするまでさらに混ぜる。
③ 溶き卵を少しずつ加え、その都度よく混ぜる。バニラエッセンスも入れて混ぜる。
④ *を合わせてふるい入れ、ゴムベラでさっくりと混ぜる。
⑤ ①を加えて軽く混ぜ、型に流し入れる。
⑥ 170度に予熱したオーブンで50~60分焼く。
良い香りがしてきて、竹串を刺して生地がついてこなければ焼き上がり。
⑦ 型から外し、粗熱が取れたら完成。
![]()
執筆者紹介: くーこ さん
つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。
学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。
趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。
コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。