Posts in Category: 苔玉に寄せて
【コラム】苔玉に寄せて Vol.120~苔玉その後
年末年始に渡って多種の植物を苔玉に仕立てました。シクラメン、カランコエ、ミニチュアローズ、小型のコチョウラン等の比較的洋風な花物等々、また、クロマツ、アカマツ、ゴヨウマツ、ウメ、ミリオンバンブー、マンリョウ、ヒャクリョウ、ジュウリョウ等の和風植物・・・・・でした。
苔玉に仕立てたこれらの植物を観て・・・・・「この苔玉、何年持ちますか?」と質問されることしばしばです。とくにマツ、ウメ等の『木本植物』の苔玉については、3~5年と永年に渡って苔玉仕立てのままで持たせ続けたい・・・・・そんな期待感をお持ちの心を垣間見ます。マツという永年植物を苔玉仕立てのままで維持し続けたい・・・・・その心の内は解ります。でも苔玉なる『狭隘な台地』で植物を維持管理し続けることは、殆んど無理・難題です。
高分子化学の発達の一面として、プラスチック製の植木鉢やプランターが大量に出回る今日、自然志向を好む園芸に親しみ・愛する人たちは、工場出荷製品プラ鉢を忌避する傾向があります。せめてプラスチック製の植付容器を自然のモノに変えてみたい、その思いの一つの現れが、鑑賞植物を」『苔玉』に仕立てる・・・・・ということになったのではないでしょうか。新春を寿いだマツ、ウメ、マンネンチク等の苔玉を、そのままの苔玉姿でいつまでも維持したい、その心は理解できますが、当のウメ、マツたちにとっては、誠に狭隘・厳しい生育環境です。
出来るだけ早急に鉢植に戻す、そして来年の新春に苔玉に衣変えして楽しむ・・・・・それが、植物たちが喜ぶ生育体系のようです。私たち園芸を嗜む者の年中行事の一環として、お考え頂いては如何でしょう。年末の生活空間に彩りを添えてくれたシクラメン等の草本植物については、苔玉から鉢植への栽培返還は感覚的に受入れやすいと思います。マツ、ウメそしてシクラメンを、私たちのライフサイクル・季節感格・年中行事にあわせて『切花』感覚で楽しむ・・・・・程の感覚で馳せています。
次は、節分にヒイラギを苔玉にしてメザシを下げて楽しむ、2月14日バレンタインの日には真紅のミニチュアローズの苔玉を、更に3月3日を目指してハナモモの苔玉を準備するなど、年中を風流心を持ちたい、老いの一徹・日々を過ごしております。

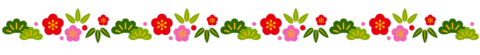
執筆者紹介 – S.Miyauchiさん
日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。
コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。
【コラム】苔玉に寄せて Vol.119~寒中の苔玉
年末です、今期一番の寒い中で、マンリョウの苔玉作りにチャレンジしました。縁起を担いで赤実のマンリョウを一株、白実のマンリョウを一株、紅白取り揃えました。単純な一本立ちの樹形に飽き足らず、幹にアルミ線(径:2.5㎜)を巻きつけて樹形に変化をつけてみました。見事な紅白の『マンリョウの苔玉』になりました。緑色の葉っぱに包まれた小さな粒の赤と白の果実たちが、早々に新春をもたらしているかの如くです。

寒さ厳しい中で、みずみずしい緑・赤・白色を精一杯演じてくれる植物たちの息遣いに『感謝』です。万両と共に千両、百両(カラタチバナ)、十両(ヤブコウジ)、一両(アリドウシ、蟻徹し)を取りそろえると『金運』に恵まれる・・・・・
『万両・千両・百両・十両、有り通し!』だ、とか・・・・・
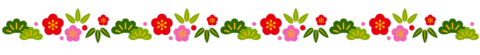
極めて狭くて小さな苔玉大地に、寒中にもかかわらず元気な生命力を見せてくれる植物たちです。油断すると枯らしてしまいます。新春を寿ぐ苔玉植物の代表に『マツ』を使うことが多いですが、『松の苔玉』を枯らしてしまったと耳にすること、しばしばです。原因は単なる水切れでした・・・!

マツ等の常緑樹は、冬でも葉っぱは元気な緑色です、少々水が切れた状態でも緑の姿を何とか維持しています。室内の空気はエアコンで乾燥・・・!緑色であったはずの松の葉っぱが茶色がかってきて、やっと水切れに気付く・・・という顛末。マツが枯れた、ツバキが枯れた、マンリョウ、センリョウもまた然り。冬季の空気は乾燥しています、更に煖房・エアコン等による強制乾燥・・・、植物たちも苔の台地も水切れ、気付いた時すでに手遅れ、という次第です。
一見しては、マツもツバキもマンリョウも緑色の元気そうな葉っぱです。気温が低いために急激な水切れ症状を表すことがない、ついつい苔玉の芯部分に水分が枯渇していることに気付かない、為に枯らしてしまう、という顛末。 噴霧器で苔玉表面に霧吹き潅水した積り、では間に合いません。苔玉の冬管理の基本は、やっぱり『水遣り』を忘れないことです。
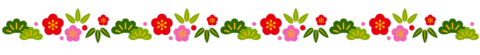
執筆者紹介 – S.Miyauchiさん
日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。
コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。
【コラム】苔玉に寄せて Vol.118~生活に根付いた園芸文化
酷暑の晩夏から、あっという間に冬の到来です。年末に向かって苔玉も忙しくなります。街中にジングルベルが流れ始める『シクラメン』の季節、そして慌ただしい年末になると、『マツ類、マンリョウ、ヤブコウジ、フクジュソウ』等々の苔玉作で大忙し・・・・・、『モミノキ』に飾り付けたXマスツリー、そして玄関周りには門松・注連縄飾り・・・・・年末・年始の生活空間は花卉園芸で満ち溢れます。

クリスマスには赤い『イチゴ』のXマスケーキ、玄関ドアに飾り付けたフラワーリース、正月は餅に鮮やかな緑色の『ミツバやセリ』をあしらった雑煮、『ニンジン・ダイコン』の紅白のなます、『サトイモ、ゴボウ、マメ類等』の煮物の食文化、蔬菜園芸で賑やかです。
手元でシクラメンの苔玉を作りながら、豊かな園芸文化に包まれた生活を享受していることに、あらためて思いを致しております。生命を維持するために野菜の種を蒔き野菜を収穫した『蔬菜園芸文化』、敷地の一角に果樹を育て、カキ、ウメ、モモ等の果実の美味を知った『果樹園芸文化』・・・・・食を満たすことに始まった『園芸』であったと思われます。食に満たされた先人たちは、ウメ、モモ等の花の美を知った『花卉園芸文化』・・・・・赤、白、紫、ピンク色と、華やかな開花のシクラメンを苔玉に作る中で、毎日の生活のなかでの『園芸文化』に思いを馳せたことでした。
愛好者の私たち、『苔玉』を賭して新しい時代の花卉園芸の一角を伝えて行きたいと願っています。
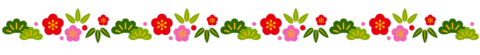
執筆者紹介 – S.Miyauchiさん
日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。
コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。
【コラム】苔玉に寄せて Vol.117~カエデの苔玉
長く続いた酷暑の候が去り、涼しい季節となってきました。秋となってはカエデの『紅葉』、赤や黄色が待ち望まれます。私たちの日本には、秋に紅葉を楽しませてくれる落葉樹木は多数あります。
でも、カエデ類程多数の品種を網羅する種(スペシィズ)は他にありません。苔玉の世界でも『カエデ類』の人気は群を抜きます。
『カエデ類』は江戸時代に多数の品種が作出され、明治、大正、昭和そして今日まで連綿と続いています。江戸・元禄の頃の江戸は、当時としては世界一の花卉園芸文化都市であったと思われ・・・・・カエデ類の愛好栽培が今日に引き継がれている次第です。こうした花卉園芸文化史の流れを、苔玉スタイルで『カエデ類』を体現できることに心ばかりの誇りを思っております。

江戸・元禄時代の花卉園芸文化は徳川将軍家によって支えられ、諸大名は江戸屋敷に優れた庭園を造り、国表に花卉園芸文化を持ち帰り伝えることになったということです。その代表的なものが肥後の国・熊本の大名・細川家であった・・・・・
肥後6花(肥後椿、肥後山茶花、肥後花菖蒲、肥後芍薬、肥後朝顔、肥後芍薬)が、よく知られています。 『カエデ類』の他に、古い江戸の時代に世界一の花卉園芸文化を築いた植物たちを列記します・・・・・
オモト、フクジュソウ、イワヒバ、マツバラン、サクラソウ、ヤブコウジ、マンリョウ、サクラ、等々・・・・・これらの花卉園芸植物を『古典植物』として分類・取り扱っている今日・此の頃です。比較的目立たない、地味な植物たちが多いですネェ!

『古典植物』として取り扱われる一群は、『苔玉』仕立て栽培に馴染む植物たちです。
令和の今日の花卉園芸愛好者の私たち、『苔玉』を賭して新しい時代の花卉園芸の一角を伝えて行きたいと願っています。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん
日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。
コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。
【コラム】苔玉に寄せて Vol.116~苔玉・植物の組み合わせ
2種類以上の植物を組み合わせて、『寄せ植え苔玉』を作る場合が多々あります。山アジサイ、ケヤキ、サルスベリ、モミジ等の落葉樹木の苔玉造りに当たっては、必ず、玉リュウノヒゲ等の背丈の低い常緑性の草類を『下草』として添植します。

落葉樹木は、晩秋 ~ 冬季の間、紅葉して落葉してしまい、寂しい景観となってしまいます。・・・・・落葉した寂しい冬の間、『玉リュウノヒゲ』は極めて丈夫な植物で、濃緑色で元気、冬の苔玉の根元を賑わしてくれます。『緑』の下草・玉リュウノヒゲが、僅かに生命活動する苔玉景観を演出してくれます。
造園、庭作りで言う『上木』、『下草』の心意気です。
アカマツ、クロマツ等の常緑樹マツ類を苔玉に仕立てる場合、その根元部分に『松ぼっくり(松笠)』と『下草』を添付・添植するなどして、苔玉景観を演出したりします。マツ類は、『松ぼっくり』が発芽してクロマツやアカマツが育った生命の循環を、苔玉界で演出します。
生命の姿、『自然の摂理』を想い描きます。

2~3種類のミニ観葉植物を、寄せ植えにした形状で苔玉に作ったりします。この場合、それぞれの植物たちの背丈比は概ね 7 : 3 : 1 ( 主 : 客 : 控 ) 程度で纏めます。
心は、『生花道』、『花生けの心』です。
私の勝手・気ままに、植物たちを苔玉の姿に衣替え・衣装直しする・・・・・『生花の心』や『庭作りの技』に学び、『大自然界の摂理』を素直に受け入れ・・・・・温故知新、多くの植物たちに学ぶ毎日です。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん
日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。
コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。